昨年はバッハを聴こうと思って、いろいろとCDを集めた。以前から比較的聴いていたのは無伴奏チェロ組曲やゴールドベルク変奏曲、マタイ受難曲あたりだった。ピアノをやっていた時期にはインヴェンション全曲とシンフォニアの半分くらいまでは自分で演奏した。それまでバッハって自分にとってはあんまりピンときていなかったが、自分で演奏してみるとバッハの天才ぶりがよくわかって、再び好奇心が芽生えた。
2019年はシベリウスをがんばって聴いたが、2020年はバッハ。きっかけは、ヴァイオリン職人の推理小説シリーズにバッハの楽曲がいっぱい出てきたこと。



このシリーズは読みやすくておすすめ。三巻目の読書日記はここでも取り上げた。
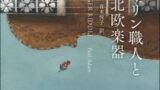
今回のバッハ音楽探究の副読本は磯山さんの魂のエヴァンゲリスト。

この本を読みながら、めぼしい曲を聴いていこうと思ったのだが、バッハの曲はたくさんありすぎて、拾い出すときりがない。
バッハと言えばカンタータなんだろうけど、曲が多すぎるので、いったんそれらは置いておいて、ヴァイオリン職人シリーズでよく取り上げられていた、無伴奏ヴァイオリンのためのソナタおよびパルティータから始まって、ヴァイオリンソナタ、ロ短調ミサ、フルートソナタなどを聴いた。
その中でも、ブランデンブルク協奏曲は、名前は当然知っていたのだが、どの曲がそれに該当するのか実は知らなくて、昨年初めて聴いて、あ、これなのかと認識した。第5番の第一楽章は超有名なので、誰でも知っていると思う。
6曲組の組曲で、明るく非常に聴きやすい。
最初はAmazon Primeで聴けるピノックのイングリッシュコンサートシリーズのものを聴いていた。曲の名称が間違っているのがあるので注意が必要。
現在の愛聴盤はベルリン古楽アカデミーという楽団のもので、ピリオド奏法で非常に演奏技術が高いと思う。

そんな中で昨年の11月に、2/20(土)に京都市交響楽団のメンバーによるブランデンブルク協奏曲全曲演奏会の開催案内をもらってチケットを取った。音楽の演奏会は客席を間引いていろいろなところで行われていたので、さすがに中止はないだろうなと、久しぶりにチケットを購入。すでに席は大部分埋まっていて、かなり左側の前から4列目を取った。
3ヶ月後の先日の土曜日、本当に久しぶりに演奏会を聴きに行った。会場は京都コンサートホールの小ホール。500人収容のホールだが、席は約半分に絞ってあり250名ほどだと思う。全席完売でほぼ満席。

小ホールは観客としては初めて入ったが、そんなに小ささは感じさせない、中ぶりのホール。府民ホールアルティという木造の素晴らしいホールが京都にはあるが、それよりは大きく感じる。アルティの収容人数は460名だそうなので、ほぼ同じ大きさなんだろう。
演奏会は、作曲順とのことで、第6番・第3番・休憩・第1番・第2番・休憩・第4番・第5番の順で行われた。
まず第6番が演奏されたが、演奏人数が6名で、そんなに少ないと思っていなかったのでびっくりした。小編成の管弦楽団のイメージだった。後から調べて知ったがこの曲はヴァイオリンなしだそうで、ヴィオラ4・チェロ・チェンバロの構成だそうだ。
曲間では演奏者の方の一人が登場して少しお話をしてくれる。これもなかなか楽しかった。
2曲目は第3番。構成は少し増えて10人程度。
なんでもそうかもしれないが、特にこの曲は演奏会で聴くべきだと思った。少人数のアンサンブルを直に見ていると、演奏者同士のフローのシンクロのさせ方がよくわかるし、こちらの精神ともよくシンクロするので、音楽にすごくのめり込める。今回の演奏会では、演奏者がすごく楽しんで演奏しているのがよくわかった。ブランデンブルク協奏曲を聴くと幸せを感じることができるなと思っていたが、演奏会を聴きに行くとこの感覚を大勢と共有できるので、よりすばらしい体験をすることができる。
2幕目は金管楽器が入る第1番と第2番。特に第2番は特殊な小さいトランペットが登場。演奏はすごく難しそうで、第1楽章はかなり苦労されていたが、第3楽章は見事な完璧な演奏だった。またいつも聴いているベルリン古楽アカデミーでは、リコーダーが入っているのだが、そこはフルートで演奏されていた。生演奏ではフルートの方が表現力も高いし音量も出るので適しているかもしれない。
最後の3幕目は第4番。この曲はリコーダーが活躍する曲だが、フルート2本で演奏された。
3幕の曲間では、チェンバロ奏者の方(中野さん)がお話しされたが、第5番は歴史上初めてのチェンバロ協奏曲で、チェンバロ演奏は大変だとおっしゃられていた。第3番の2楽章のチェンバロカデンツァはすばらしかった。お話も面白く、第5番楽しみ。
で、最後の第5番。第一楽章の特に最初の弦楽とフルートの合奏は超有名だけど、途中からチェンバロ独奏になる。これが超絶技巧で、すばらしい。確かに演奏大変だろうなと思った。チェンバロは音量の起伏はつけにくそうな楽器で、ロマン派以降には合わないと確かに思うけど、独特の音色でこんな超絶技巧演奏を聴かされると、素晴らしいなと思う。
途中の解説で、ブランデンブルク協奏曲は、バッハのケーテン時代、ブランデンブルク候に献呈された協奏曲だが、ブランデンブルクでは一度も演奏されなかったという逸話が紹介されていた。ブランデンブルクの演奏レベルはあまり高くなく、演奏できる奏者がいなかったそうだ。
前述の本でもわかることだが、バッハ自身もオルガン演奏の腕前はピカイチだったらしく、バッハの作曲する楽曲は高い演奏レベルを要求するものだった。ピアノでバッハをやる人は、バッハきらい!って人とバッハ大好きの両派に別れるようだが、たった二声の対位法で書かれたインベンションでさえ、初学者には高いハードルで、嫌いになる人は多そうだ。でも、たった二声でも本当に深い音楽が作れるんだと驚嘆することになるので、ここからバッハに引き込まれる人も多そう。(私はその口)
久しぶりの演奏会、大満足。またそのうちいいプログラムがあったらチケットを取りたいと思う。



コメント