交雑する人類-古代DNAが解き明かす新サピエンス史
デイヴィッド・ライク 日向やよい訳
[amazonjs asin=”B07G9WH7X8″ locale=”JP” title=”交雑する人類 古代DNAが解き明かす新サピエンス史”]
11/23から12/25まで約1ヶ月かかった。平日限定昼30分の読書時間がほとんどなので、だいたい10時間強くらいかと思う。
かなり手応えのある本で、読むのがちょっと大変だった。
全体は3部構成で、第一部が古代人のDNA解析による手法の説明が結構詳しく書かれている。第二部は副題にもなっているDNA解析によって明らかになりつつあるホモ・サピエンスの歴史について。ヨーロッパ・中東・南アジア・アメリカ・東アジア・オセアニア・アフリカの各地域ごとに、10万年前くらいからのホモ・サピエンスの動きと各グループの交雑の様子を、2017年くらいまでの最新の世界の研究結果に従い解説してくれる。第三部はDNA解析が発明されたことによる考古学等にもたらされた変化や、今後の展開、倫理・道徳など多方面からの見地からの問題点等を論じる。
筆者は純粋に生化学者なので、科学の切り口によって論が展開される。科学の発展により、いずれ事実が偏見や差別等を駆逐するという見地に立っている。科学を信じるものは共感を持って読めると思うが、そうでないとちょっとアレルギー反応が起こるかもしれない。
第一部はまるで数学や科学の教科書を読みすすめるようにゆっくり読まないと、論理展開についていけない部分があるので、さらさらとは読めない。サラッと読んでしまうと、結局よくわからないで終わってしまう可能性があるので、ゆっくり読む。
その科学的手法によって何がわかってきたかもこの部で紹介されている。ホモ・サピエンスはネアンデルタール人と交雑した証拠はあるが、常に交雑していたわけではなく、その期間と機会は限られていたようだ。
第二部はそれぞれの地域でどのような移動と交雑が行われてきたかにスポットを当てる。科学的なデータを紹介しながら研究の流れを追うので、人類史だけに興味がある場合は少々まどろっこしいかもしれない。しかし、実際には発見されていないゴースト集団がDNA解析によって予言され、その後その人骨が発見されるということが複数回起こっており、非常に興味深い。まだまだDNA解析による古代史研究は始まったばかりであり、ヨーロッパは比較的よく調べられているが、東アジアなどはまだまだこれからであり、今後の展開が期待される。
第三部はDNA解析による考古学が社会的にどんな影響を及ぼしたか、そして今後どんな影響を及ぼすか、筆者の意見・考え方を中心に展開される。人種問題や遺伝の問題はナイーブで取り扱いが難しいので、科学的見地と社会的見地では摩擦が起きる。それによって引き起こされている問題と、筆者の考えが述べられている。
科学に信頼を置く私のようなものにはスカッとした意見だが、今の世界を見ていると、真実というものもまた一つではなく、立場・歴史によってブロードなスペクトルを持つ。それを考慮すると、科学的にはっきりした結論も、社会に対して説得力を持つには時間がかかるだろう。しかし時間が結局は解決するだろうと、私もまた思う。
さて、この最新の人類史の知見を、もうちょっとドラマティックに書いた本も読んでみたいなと思う。何冊か候補はあるので、次の機会に読んでみたいと思う。
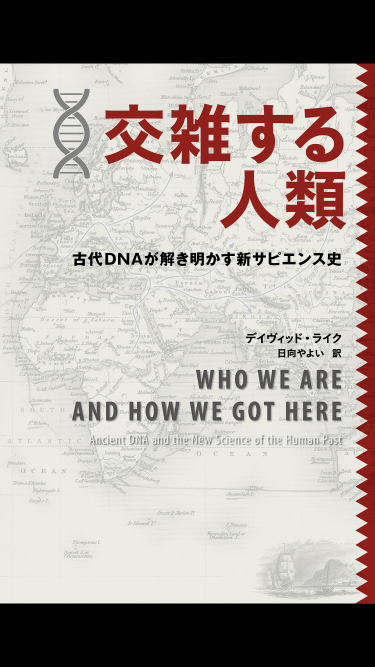


コメント